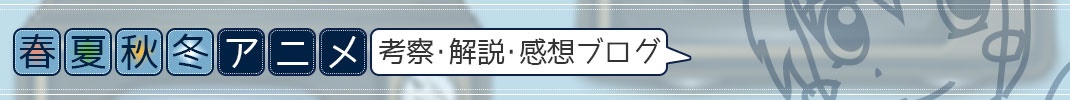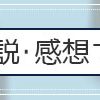皆々様こんにちは。
今回は言わずと知れたアニメ界の巨匠、宮崎駿の10年振りの新作『君たちはどう生きるか』を扱ってみたいと思います。
今回の新作は事前の情報開示が一切行われていないという謎だらけのスタート。
おまけに作品自体も非常に抽象的なうえに賛否両論ということもあって、なかなか見ごたえがありました(笑)
ではではどんな作品だったか、じっくり振り返ってみましょう。
目次
注意書き
この記事は性質上、多大なネタバレを含みます。
一切の事前情報を開示しなかったジブリに敬意を払い、あらすじ自体は載せませんが、作品について語る過程で内容はガンガン触れていきます。
そのため、未鑑賞の方はご注意ください。
また、この記事はまだ一回しか鑑賞していない人間が備忘録兼メモ代わりに書いている節があるため、記憶違いや誤認が含まれている可能性が多大にあります。
おまけに本作において重要なファクターを占めるであろう吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』は未読の状態で書いています(そのため、あえて『君たちはどう生きるか』には触れないで執筆しています)。
そのため、不完全な状態で書いている記事であることは何卒ご了承くださいませ。
もちろん、私の認識違いに対するご指摘・ご意見は大歓迎です。
さて、前置きが長くなりましたが、以上を踏まえたうえでお読みいただけると幸いです。
眞人が生きる世界
では、まずは本作の主人公である眞人、そして彼を取り巻く人物や世界について触れてみましょう。
牧眞人
本作の主人公である牧眞人ですが、ジブリでは珍しいなかなか屈折した人物であることが窺えます。
礼儀正しく、勝一や夏子に調子を合わせられる器用さもある一方で、常に本音を抑圧しており、ふとした弾みで激情が露わになる場面もありました。
とりわけ転校したてで同級生と早速喧嘩したり、喧嘩を誤魔化すためとはいえ自傷行為のように頭を石で殴ったり、いくら不気味とはいえアオサギを過剰に敵視したりする場面では、年相応ながらも強い暴力性を内包していることすら感じさせましたね。
他方で、火事で命を落とした母の久子を想ったり、彼女の残した小説を読んで涙を零すなど、年相応のあどけなさや感受性も持ち合わせているようでした。
また、事切れた老ペリカンを手厚く埋葬したり、なんやかんやで仲がよくなったアオサギを「友達」というなど、心優しい一面も持ち合わせています。
しかし、眞人はその優しさでさえも(少なくとも序盤では)日常生活でのストレスで抑制していることが窺えますね。
ジブリに登場する男の子の主人公は『崖の上のポニョ』の宗介や『もののけ姫』のアシタカのように感情が豊かだったり、真っすぐとした人物が多かった中で、感情の起伏をあまり見せない眞人はいささか異色の雰囲気を放っているといえます。
うっとうしい父と偽りの母
なかなか危うげでひねくれ者の眞人ですが、彼の両親もなかなか面白いキャラクターでした。
まず父親の勝一ですが、これまた豪快で見栄っ張りな人物。
転校したての眞人を車で送って自分の財力を見せつけたり、300円の寄付金で校長を思いのままにしようとするなど、よくも悪く金持ちらしい豪胆な振る舞いが印象的です。
まぁ豪快なあまり眞人の繊細な機微を全く拾えていないのは残念ですが…。
そんな勝一ですが、作中の描写を見る限り、どうやら軍需工場を営んでいるようです。
羽振りのよさは戦時中で稼ぎまくっているからなんでしょうけど、サイパン陥落に笑いながら触れるなど、当時の政府や軍部の根っからのシンパというわけではなさそうですね。
むしろ世間を斜めに見ながらうまく世渡りする人物のように感じました。
また、行方不明になった眞人や夏子を懸命に捜したり、2人を見つけるなり真っ先に駆けつけるなど家族想いな人物であることが窺えます。
そしてそんな勝一と再婚し、子供(眞人の弟)を身ごもった夏子ですが、彼女もまた眞人のように本音を抑圧する人物のように感じました。
母親なろうと眞人に優しく接しますが、肝心の眞人はなかなか心を開かず、つわりでしんどい時にはそっけない態度を取られていました。
そもそも勝一の前妻は姉の久子…実の姉を喪った悲しみも少なからずあるのでしょう。
それに加えて帰りの遅い正一のフォロー不足、妊婦特有の体調・精神面の不安定さもあって、実は表に出していないだけでかなり追いつめられていたのかもしれません。
夏子が突然下の世界に行ってしまったのも、これが原因と考えられるでしょうね。
以上の点がわかることは、眞人の両親(厳密には実父と継母)と眞人の間にはすれ違いがあり…互いが互いの本音に触れられていないという点です。
勝一や夏子が心を閉ざす眞人の本音に触れられないように…眞人もまた父の愛情や母の想いを眞人はうまく受け止められず、むしろ拒もうとすらしているわけです。
ただ、眞人が勝一と夏子を受け入れられないでいる理由はわらかなくもありません。
そもそも夏子は久子の妹、つまり眞人の叔母にあたる人物です。
親族が突然親になるのは誰だって戸惑いますし、いくら叔母でも眞人にとって久子に代わるものではありません。
加えて正一と夏子が人知れずキスをしているところを眞人は目撃していました。
親族とはいえ他人が唯一無二の存在である母親の席におさまり、さらに両親が男女として愛し合っている。
眞人からしたら、両親が汚らわしい他人に見えてしかたなかったことでしょう。
そして同時に、親という不変と思われていた存在が既に失われていることを、眞人は思い知ったわけです。
上の世界
ここでは作中の世界を見ていきましょう。
便宜的に「上の世界」と呼称していますが、これは眞人が生きる現実世界を指します。
本作は第二次世界大戦中の日本が舞台であり、作中では出征に向かう旧日本軍の兵士の姿も描かれています。
当時の日本について詳しく語られる場面は少ないですが、下の世界を支配する大叔父様は上の世界を「醜い」といった言葉で酷評するなど、決してよい世界とは描かれていません。
久子が命を落とした火事や、パニックに陥る人々の描写を見ても、混沌として暗澹とした世界観が描写されている印象です。
また、眞人は勝一と久子や夏子の実家に疎開しますが、(勝一のせいとはいえ)眞人をいじめる同級生がいるなど、そこも眞人にとって居心地のよい場所ではありませんでした。
何より久子を喪い、心を許せない勝一や夏子と共に生きねばならず、おまけに夏子のお腹には母の違う弟がいる。
眞人にとって、上の世界は息がつまるような場所であるといえるでしょう。
下の世界
時代背景や眞人の心情もあって居心地がよいとはいえない上の世界に対し、夏子を助けるために眞人が踏み入れた下の世界は空想に満ちたファンタジックな世界でした。
しかし冒険に心ときめくような、自由で豊かな世界…というわけでもありません。
下の世界は幻想的な場面こそあるものの、いきなり「我を学ぶ者はタヒす」と門に記された墓が出てきたり、人を食うインコが出てきたり、通りがかるだけで攻撃してくる悪意を持った石があったりと、個人的には不気味さとカオスに満ちた世界のように感じました。
下の世界は大叔父様が作り上げたものだとされていますが、キリコや久子のような上の世界の人間の過去の姿が出てきたり(久子は上の世界の記憶がある模様)、セッ生ができない亡霊のような住人がいたり、生まれる前の魂があったりと、まるで現在と過去が混在したあの世のような側面もあります。
一方で、大叔父様がコントロールしているというわりには、人間を食うインコが牛耳っているなど、人間に対して排他的な側面があることも窺えますね。
また、作中では老ペリカンが「どこまで飛んでも島に戻ってしまう」と語るなど、狭い世界であることが示唆されています。
個人的に、本作で描かれた下の世界は原作版の『風の谷のナウシカ』に出てくる庭園やシュワの墓所のようなイメージを持ちました。
本作は「冒険活劇ファンタジー」と銘打っていますが、その舞台である下の世界は幻想的でありつつも、どこか閉塞的で、生々しいまでに暴力とタヒに満ちているものです。
そして、大叔父様が世界の維持を眞人に託そうと考えているなど、下の世界はすでに限界を迎えつつありました。
これらの点を踏まえると、下の世界はむしろ「すでに幻想がタヒにつつある世界」と評すべきかもしれません。
堕ちた鳥たち
本作はあまりにメタだらけなので1回程度の鑑賞で全てを拾うのは難しいですが、せっかくですし1つは触れてみましょう。
今回取り上げたいのは「鳥」です。
本作では眞人を下の世界へ誘うアオサギを始め、ペリカンやセキセイインコが印象的な場面で登場していましたが、これらの鳥にはある共通点はあります。
それは「まともな状態ではない」という点です。
中身が人になっている半鳥人のアオサギはいわずもがな、わらわらを襲うほどに困窮し飛ぶことができないものすら増えているペリカン、すでに飛ぶのをやめ二足歩行で行動するうえに人を食うセキセイインコと、作中に登場する鳥はまともではないといってもいい状態です。
鳥は自由や解放などといったポジティブなメタファーとして使用される印象がありますが、本作における「鳥」はそのようなメタファーとはかけ離れた存在といってもいいでしょう。
むしろ老ペリカンのセリフや大叔父様の跡目を狙う大王インコを踏まえると、「鳥であることを喪いつつある/喪ってしまった」と捉えるべきでしょうか。
そう考えると、アオサギという存在はなかなか興味深いものがあります。
彼は文字通り鳥の皮を被ることで姿と能力を偽装していましたが、眞人に風切の7番を矢羽に使った矢でいられて嘴に穴を空けられただけで飛べなくなっていました。
またアオサギには眞人を挑発するような発言をしていると嘴の中から歯や鼻、果てには顔の一部が露出する場面がありました。
いささか気取った表現をするなら、アオサギは鳥の皮を傷つけられるか、本性を露わにすると鳥としての完全性を喪う存在といえるでしょう。
となると、個人的に作中における鳥は「完全性」や「純粋性」を象徴していると捉えたいところです。
そしてここから逆説的に考えると、作中に登場するどこか歪んだ「鳥」達は、完全性や純粋性を喪失した、あるいは偽装している存在として捉えられそうですね。
また、この捉え方をすると下の世界がもたらす作用もわかってきます。
一見すると純粋な鳥に見えるペリカンですが、老ペリカンの言葉を踏まえるなら下の世界に連れてこられたことで鳥の完全性を喪いつつあると示唆されていました。
そしてセキセイインコ達は下の世界では鳥ではなく権力や欲望に執着する人間のように描かれている一方で、上の世界に出ると瞬く間に普通の姿に戻っています。
つまり下の世界は存在の完全性や純粋性を奪う空間ともいえるわけです。
うろ覚えながらも解釈
さて、ここではうろ覚えながらもどうにか編み出した解釈を5つ提示していきたいと思います。
空想の限界
先述したように、下の世界が存在の完全性や純粋性を奪う空間だと想定した場合、大叔父様の言動が興味深いものになります。
大叔父様は眞人に下の世界の維持を任せようとしますが、その際に「自らの血を継ぐ悪意のない人間」が後継者の条件であると明かしていました。
下の世界が完全性や純粋性を奪う作用を持つにも関わらず、その主は完全性や純粋性に固執しているという点は、なかなかの皮肉です。
そもそも主に悪意がなくとも、いくら世界を構成する石に悪意が宿るものがあったからといっても、下の世界は先述したようにまともな世界ではありません。
人を見つけるなり我先に包丁やフォークを持ち出して食おうとするセキセイインコが跋扈し、通りがかるだけで攻撃してくる石がある。
実質的に下の世界は空想からほど遠い生々しい暴力のリアリズムが支配している世界であり、その点においては戦争が起こっている上の世界とほとんど違いがありません。
確かに大叔父様が石に魅入られ、下の世界を生み出した当初は空想に満ちた美しい世界があったのかもしれません。
わざわざペリカンを連れ込んだのも、そんな世界を彩るためでもあったのでしょう。
そんな下の世界がこのような状態になった経緯は詳しく語られていません。
ただ、大叔父様の跡目を狙う大王インコの振る舞いを見る限り、自由で空想的な活力に満ちた下の世界の力に魅入られた存在が争ったり、ペリカン達のように下の世界の限界点を前に疲弊した結果と見るべきでしょう。
つまり下の世界そのものが人に夢や活力を与え、完全性や純粋性を守る空想がすでに限界を迎えていることを示しているといえます。
誰がための暴力
下の世界は美しくも残酷な暴力のリアリズムに満ちた世界でした。
ある意味あの暴力性こそが下の世界の限界を決定づけていたといえますが、本作ではその暴力の別の側面も描かれていました。
例えば眞人は、アオサギを警戒し、自ら弓矢を作って戦いますが、これは彼の無鉄砲さだけでなく、勇敢さを如実に示唆しています。
アオサギの狡猾さに惑わされず、自らの意志で夏子を助けに行くという気持ちを示しているわけです。
下の世界でキリコが魚を狩り、解体する場面もある種の暴力ともいえます。
しかし、彼女の行いは生き物の命を奪えない住人や生まれ変わろうとするわらわらのためであり、私利私欲ではありません。
眞人自身も体験しますが、それは慎ましいコミュニティを成り立たせるために欠かせない営みです。
それはわらわらを飛ばすために、多少の犠牲を承知でペリカンを火で追い払ったヒミにも同じことがいえるでしょう。
この暴力は営みとして必要な暴力であり、人を食うために暴れ回るインコや、戦争やいじめっ子との喧嘩とは一線を画しています。
そしてキリコやヒミはこの暴力を穢れや咎を引き受けることも厭わず、自ら引き受ける人物と捉えられます。
たとえ無垢でいられずとも
下の世界の限界の陰には大叔父様が無意識に抱えている矛盾があるようにも感じられました。
完全性や純粋性を求める者は決して完全でもなければ純粋でもありません。
それらを求めている時点でその者は完全でも純粋でもなく、同時にその者が見初めた者もまた完全でも純粋でもないわけです。
それを端的に示唆しているのが、大叔父様と眞人の終盤のやり取りでしょう。
大叔父様は穢れのない13個の石を譲る際、「自らの血を継ぐ、悪意のない人間」を条件としていました。
まさに血縁(完全性)・悪意のない(純粋性)というわけですが、眞人は「自分には悪意がある」として拒否します。
事実、眞人は正一や夏子を疎ましく思い、友人と喧嘩し、嘘を吐くために自らを傷つける(その傷は悪意の象徴として扱われていました)人間です。
必ずしも一点の穢れのない人間ではありません。
しかし、自身の悪意を自白した眞人の姿は凛々しいものでした。
下の世界での冒険を、まさに自らの糧とした者の姿といえます。
そんな眞人だからこそ、大叔父様は心惹かれたのでしょう。
先述したように、完全性や純粋性を完全に維持している存在はいません。
上の世界はもちろん、空想の世界である下の世界でさえも、閉塞と欲望の果てに完全性や純粋性は喪われていきます。
それを踏まえると、純粋な美しい子どももまた存在しません。
だけど悪意や穢れを自覚し受け入れる子どもこそ本当に美しい。
完全性や純粋性を持つ存在はおらず、それらを希求する存在は完全でもなければ純粋でもない。
しかし自らの不完全性と不純性を理解し受け入れる存在にこそ、逆説的に完全性や純粋性が宿るのかもしれません。
家族の終わり
眞人の屈託は命を落とした久子や、正一や夏子が起因するものでした。
いうなれば久子のタヒによる「家族の欠落」と、正一と夏子の再婚による「完全で純粋な家族像」の崩壊が眞人に暗い影を落としたわけです。
そもそも家族の存在は決して永遠ではありません。
時が経たり、予期せぬ事態が起こり、常に変貌していくものです。
しかし大叔父様と同じように、家族もまた完全性や純粋性を求められるものでした。
それは継母を受け入れられなかった眞人と同様に、夏子も感じていたことでしょう。
夏子が産屋にこもったのも、完全で純粋な母親を目指していたことに疲れたことが原因かもしれません。
しかし、最終的に眞人はそんな夏子を受け入れることを選びました。
まだ久子のことは引きずっている(ヒミへの接し方にそれが現れています)が、眞人からしたら新しい命を宿した夏子を見捨てることはできません。
何より、自分が夏子を追いつめた一因であることを、彼もまた自覚していたのでしょう。
同時にそれは、眞人が抱いていた完全で純粋な家族が終焉を迎え、新たな家族を受け入れる準備ができたということも意味します。
しかし、眞人はまだ久子のことを完全に切り捨てられてはないないのでしょう。
夏子を「夏子母さん」と、他者性を残した呼び方にしているのは、その表れかもしれません。
夢の墓にて
さて、ここまでざっくばらんに書いてきましたが、一応総括といきましょう。
個人的に本作は「物語の終わり」を描いていると捉えています。
本来、下の世界は空想に満ちた、それこそ美しい虚構が繰り広げられる物語的な世界だったのでしょう。
しかし、悪意や欲望によって下の世界はどこか歪んだ世界になっていました。
そもそも完全で純粋なものが存在しないように、物語もまた完全で純粋なものではありません。
大叔父様でさえも悪意や穢れを持つ石を完全に取り除けなかったことからわかるように、悪意や穢れによって下の世界は常に危ういバランスの上で成り立っていました。
そして大叔父様の役目の承継を拒否された時点で崩壊するリスクがある以上、物語は既に限界を迎えていたというわけです(墓はまさにその象徴というわけです)。
また、本作においては世界を作る=物語を作ること自体も罪悪であり、また自身の本来の在り方を喪わせる行為であると示唆されています。
実際、大叔父様は人間性を喪失している状態でしょうし、それを示すかのように墓には「我ヲ學ブ者ハタヒス」と記されていました。
ある意味これは悲惨な状況ですよね。
上の世界が戦時中と最悪な状況になっている一方で、下の世界は限界を迎えつつあるということは、よくいわれるような「現実の逃避先としての虚構」が成立しなくなっているといえるからです。
そしてそんな世界だからこそ、本作はタイトルで問いかけているのでしょう。
「君たちはどう生きるか」、と。
一方で、世界には眞人のような子どももいます。
己が抱える悪意と穢れを認め、同じように悪意や穢れの中を生きるアオサギ、キリコ、そしてヒミのような人とつながりを持ち、ろくでもない世界でも真っすぐ生きていく覚悟を決めた子どもが。
きっと彼なら、物語が力を失くしても生きていけるに違いない…いや、そうあってほしい。
本作において、宮崎駿はそんな想いを込めたのではないでしょうか。
また、個人的に本作は物語に対する観客も描いていると捉えられます。
これまで宮崎駿は多くの観客、とりわけ子どもに向けて多くの物語を作り上げてきました。
しかし現実は物語のようにいかず、物語もまた時を経ることに力を喪っていきます。
そしてリアルタイムでその物語を見た子ども達も大人になっていつしか忘れていく。
でも、いつしか忘れられる物語であっても、それを見た子どもがよい大人になっていてほしい。
自分の運命を知っても、神隠し中の記憶を忘れても、眞人を産み育てる未来を選んだヒミのように。
つまり本作は、恐らく年齢的にもう新作を作らないであろう宮崎駿からの観客に向けたラブレターであると同時に、お別れの挨拶ではないでしょうか。
他方で、本作は宮崎駿が観客にまだ未練を残しているようにも感じられました。
できることなら、物語をほんの少しでも長く覚えていてほしい。
ラストで眞人がまだ下の世界のことを覚えている終わり方にしたのは、その未練の表れなのかもしれません。
なお、一部界隈で、本作が「ジブリを象徴している」のではないかと考察されていますが、個人的にこの説には一部同意しています。
確かに大叔父様=宮崎駿、下の世界=ジブリと捉えることはできるでしょう。
とりわけ第一印象から本作はこれまでのジブリのパロディ的な要素が多くあると感じました。
わらわらはコダマ(『もののけ姫』)、塔は『ハウルの動く城』、墓はシュワの墓所(『風の谷のナウシカ』)など、これまでの作品に登場したキャラクターやモチーフに近いものが描かれていますし、キリコの庭での描写や穴ぐらを移動するシーンなど、一部のカメラアングルや構図は過去作を連想させるものがいくつかあります。
ただ、個人的に作者のパーソナリティに迫るような考察はあまり意味がないと思うため、あえて触れていません。
でももしちょっとだけ触れるとしたら…。
大叔父様は「自らの血を継ぐ者」を後継者の条件に入れていました。
しかしその条件をクリアしている眞人は大叔父様の申し出を拒否しています。
もしかしたら、これは宮崎駿が実子に向けたメッセージ…なんてこともあるかもしれません。
『君たちはどう生きるか』感想
いやー一回だけの鑑賞だとやっぱりしんどいですね(笑)
今回は書く時間をしっかりとれなかったので、微妙な仕上がりになってしまっているかと思います。
微妙なところは、おいおい追記・修正をしていく次第なので、そこはどうかお許しください(笑)
さて、賛否両論多い今作ですが、個人的にはいろいろ複雑な気持ちで見ていました(笑)
ジブリ、もとい宮崎駿監督作品は子どもの頃から見ていましたし、いろいろ思い入れがありますからね。
ここでは書きませんが、思うところは結構ありましたし(笑)
まぁ何はともあれ、『君たちはどう生きるか』、観ておいて損はない作品かと思います。
賛否両論になるのもわかるくらい抽象的な物語ですが、『風立ちぬ』と原作版の『風の谷のナウシカ』を足して2で割った感じと思えば、とっつきやすくなるかもしれません。
とりわけ本作で描かれていることは原作版の『風の谷のナウシカ』で描かれていることにわりと符合する気もするかも…。
あくまで個人の感想なので、参考になるかはわかりませんが(笑)
さて、この記事もこれで終わりです。
また別の作品の記事でお会いしましょう~。
▼当サイトでは他にも多数のアニメを考察しています!
最新情報をお届けします
Twitter で2017春夏秋冬アニメ考察・解説ブログをフォローしよう!
Follow @anideep11